イタチの好む獲物の特徴は?【体重200g以下の小動物が中心】被害予防に役立つ3つの重要ポイント

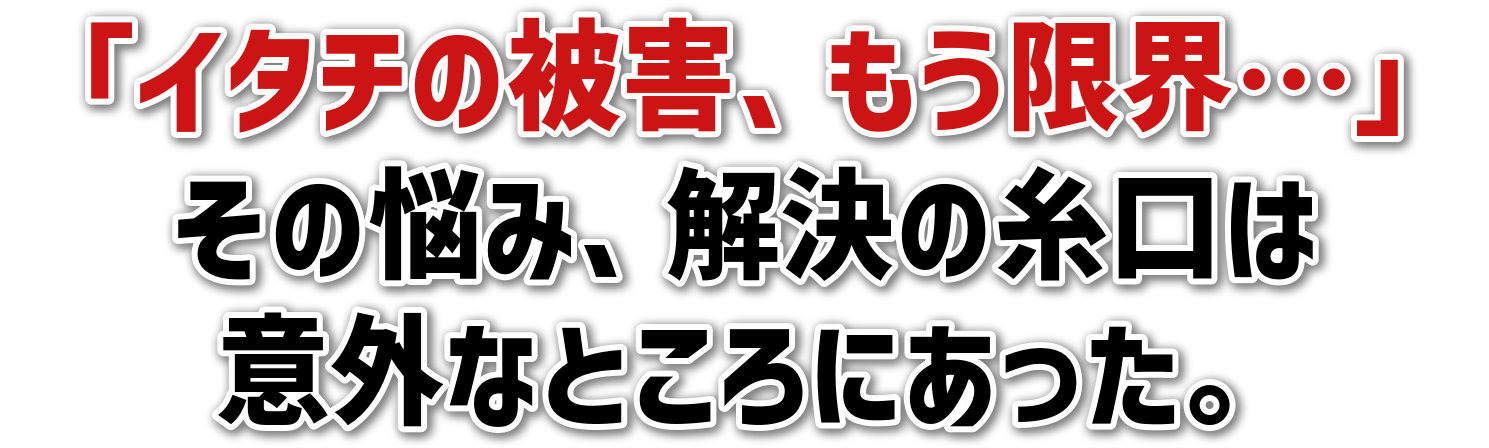
【この記事に書かれてあること】
「イタチの被害に悩まされているけど、どうしたらいいの?」そんな声をよく耳にします。- イタチが好む獲物の体重は50〜200gが理想的
- 小型哺乳類や小鳥がイタチの主な獲物
- イタチの食性は季節や地域によって変化する
- 獲物の栄養価と捕獲のしやすさがイタチの好みを左右
- イタチの被害対策には獲物の特徴を理解することが重要
実は、イタチ対策の鍵は彼らの食生活にあるんです。
イタチが好む獲物の特徴を知れば、効果的な対策が見えてくるんです。
体重200グラム以下の小動物が主なターゲット。
でも、季節や地域によって好みは変わります。
この記事では、イタチの食卓の秘密に迫り、あなたの家や農地を守る方法をご紹介します。
イタチとの知恵比べ、一緒に始めましょう!
【もくじ】
イタチが狙う獲物の特徴とは?200g以下の小動物が中心

イタチが好む獲物のサイズは「50〜200g」が理想的!
イタチが最も好む獲物の体重は、なんと50〜200グラムなんです。これはイタチにとって、ちょうど食べごろのサイズなんですね。
なぜこのサイズなのか、気になりますよね。
「イタチさんの胃袋に合わせてるの?」なんて思うかもしれません。
実は、イタチ自身の体重と深い関係があるんです。
イタチの体重は通常300〜700グラム。
つまり、好む獲物は自分の体重の半分以下なんです。
これには重要な理由があります。
- 捕まえやすい:小さすぎず大きすぎず、ちょうど良いサイズ
- 運びやすい:巣穴まで持ち帰れる重さ
- 食べきれる:無駄なく栄養を摂取できる量
「ガブッ」と一口で仕留められるサイズが理想的なんです。
大きすぎる獲物だと、逆に反撃されるリスクも。
そのため、体重200グラム以下の小動物が、イタチの「おいしいごはん」リストの上位を占めているというわけです。
小型哺乳類がイタチの「大好物」ランキング上位に
イタチの食卓に並ぶ主役は、なんといっても小型哺乳類です。特に、ネズミ類はイタチの大好物ランキングでトップクラスの人気を誇ります。
イタチの「うまうま」リストを見てみましょう。
- ネズミ類(ハツカネズミ、ドブネズミなど)
- モグラ
- リス
- 小鳥(スズメ、ウグイスなど)
- ウサギ(子ウサギ)
それは、すばしっこくて栄養たっぷりということ。
イタチにとっては、「おいしくて健康的」な理想の獲物なんです。
「でも、なんでネズミが特に人気なの?」って思いますよね。
実は、ネズミはイタチにとって完璧な食事なんです。
サイズ感はもちろん、タンパク質が豊富で脂肪分も適度。
しかも、ネズミは繁殖力が高いので、いつでも手に入る便利な食材というわけ。
イタチにとって、ネズミを捕まえるのは楽しいゲームのようなもの。
「キュッキュッ」と鳴きながら素早く動き回るネズミを追いかけるのは、イタチの狩猟本能をくすぐるんです。
まさに、イタチ版の「猫とネズミ」ゲームといったところですね。
イタチが200g以上の獲物を狙う「レアケース」とは?
イタチは普段、体重200グラム以下の小動物を好んで狙います。でも、時には「えっ、そんな大きいの?」というような獲物に挑戦することもあるんです。
これって、まさにイタチの「レアケース」なんですね。
では、どんな時にイタチは大物狩りに挑戦するのでしょうか?
- 食糧難の時期:小さな獲物が見つからない時
- 繁殖期:栄養をたくさん必要とする時
- 群れでの狩り:仲間と協力して大きな獲物に挑む時
小さな獲物が冬眠していたり、数が少なくなったりすると、イタチは仕方なく大きな獲物に目をつけるんです。
「お腹がすいたら何でも食べちゃう!」という感じですね。
また、繁殖期のメスイタチは、栄養をたっぷり摂る必要があります。
そんな時、体重200グラムを超える獲物でも、「よーし、挑戦だ!」と意気込んで狙うことがあるんです。
さらに、稀にですが、イタチが群れで行動する際には、協力して大きな獲物を倒すこともあります。
「みんなで力を合わせれば、大きいのだって倒せるぞ!」という感じでしょうか。
ただし、こうしたケースは本当に珍しいんです。
イタチにとって、大きすぎる獲物は危険も伴います。
「ガブッ」と噛みついたはいいものの、逆に反撃されてケガをする可能性だってあるんです。
だから、イタチは基本的に「無理はしない」主義。
自分の体重の半分以下の獲物を、コツコツと狩る賢い動物なんです。
イタチの獲物選びは「自身の体重」が重要な判断基準
イタチの獲物選びには、実は「計算」が隠されているんです。その重要な判断基準が、なんとイタチ自身の体重なんですね。
「えっ、イタチって体重計乗ってるの?」なんて思うかもしれませんが、そうではありません。
イタチは本能的に、自分の体重の約半分以下の獲物を選ぶんです。
これには、とても賢い理由があるんですよ。
- エネルギー効率:獲物を捕まえるのに使うエネルギーと、獲物から得られるエネルギーのバランスが最適
- 安全性:自分より大きすぎない獲物なら、反撃のリスクが低い
- 運搬のしやすさ:巣穴まで持ち帰れる重さ
この子が狙う獲物は、だいたい50〜250グラムくらい。
「ちょうどいい!」というサイズ感なんです。
イタチにとって、獲物を捕まえるのは命がけの仕事。
「ガブッ」と一口で仕留められるサイズが理想的なんです。
大きすぎる獲物だと、逆に反撃されるリスクも。
そのため、自分の体重を基準に獲物を選ぶんですね。
さらに、イタチは獲物を巣穴まで持ち帰ることが多いんです。
「よいしょ、よいしょ」と運べる重さというのも大切なポイント。
自分の体重の半分以下なら、なんとか運べるというわけです。
こうして見ると、イタチって意外と賢い動物だと感じませんか?
自分の体重を基準に、エネルギー効率や安全性、運搬のしやすさまで考えて獲物を選んでいるんです。
まさに、自然界の「賢い食事プランナー」といえるでしょう。
獲物を捕まえやすい「夜間」がイタチの活動のピーク!
イタチの活動時間のピークは、なんと夜なんです。「えっ、イタチって夜型なの?」と驚く人もいるかもしれませんね。
実は、この夜行性こそがイタチの狩りの秘訣なんです。
イタチが夜に活動する理由は、獲物を捕まえやすいからなんです。
具体的には、日没後2〜3時間がイタチの活動のゴールデンタイムです。
この時間帯、イタチにとって都合の良いことがたくさんあるんです。
- 獲物が活発に動く:ネズミなどの小動物も夜行性
- 暗闇を利用できる:イタチの目は夜でもよく見える
- ライバルが少ない:昼行性の捕食者が活動していない
その鋭い嗅覚と聴覚を駆使して、獲物を探すんです。
「ん?あそこで何か動いた!」と、獲物を発見したら素早く襲いかかります。
イタチの目は、人間の100倍以上の光を集める能力があるんです。
だから、暗闇でも獲物の姿がはっきり見えるんですね。
一方、獲物の方は暗くてよく見えない。
これって、イタチにとってはとても有利な状況なんです。
また、夜は他の捕食者が活動していないので、競争相手が少ないんです。
「よーし、今夜はたくさん食べるぞ!」とイタチも意気込んでいるかもしれませんね。
ただし、イタチは完全な夜行性ではありません。
食べ物が少ない時期には、昼間に活動することもあるんです。
でも、基本的には夜型生活。
この習性を知っておくと、イタチの被害対策にも役立ちますよ。
夜間にはイタチの活動を特に警戒する必要があるというわけです。
イタチの食性と獲物の特徴を徹底比較!季節や地域による違いとは

イタチの食性は「動物性vs植物性」どちらが主食?
イタチの食性は、動物性が主食で、植物性は副食といった感じです。でも、季節によって変わるんですよ。
イタチさんの食卓を想像してみましょう。
「今日のごはんは何かな?」とイタチさんが言いそうですね。
メインディッシュはやっぱり動物性のおかず。
特に小型の哺乳類や鳥類が大好物です。
でも、イタチさんも時々野菜が食べたくなるんです。
特に秋から冬にかけては、果物や木の実なども食べます。
「たまには野菜も食べないとね」って感じでしょうか。
イタチの食性を細かく見てみると、こんな感じです。
- 動物性食品:約70%(ネズミ、小鳥、卵、昆虫など)
- 植物性食品:約30%(果実、木の実、草の根など)
春から夏は動物性の割合が増え、秋から冬は植物性の割合が増えるんです。
「夏はお肉をモリモリ、冬は果物でビタミン補給!」というわけです。
イタチが動物性を好む理由は、高タンパクで栄養価が高いから。
でも、植物性の食べ物も大切な栄養源なんです。
例えば、果物に含まれるビタミンCは、イタチの健康維持に欠かせません。
面白いのは、イタチの食性が環境に適応する能力です。
食べ物が少ない時期には、普段あまり食べないものでも口にします。
「食べ物の好き嫌いは言っていられないよ」というところでしょうか。
このようにイタチの食性を知ることで、イタチの行動パターンや生態をより深く理解できます。
そして、その知識は効果的なイタチ対策にも役立つんです。
都市部のイタチvs農村部のイタチ!好む獲物の違い
都市部のイタチと農村部のイタチでは、好む獲物にちょっとした違いがあります。環境が違えば、食べ物も変わるんですね。
まず、都市部のイタチさん。
こんな感じで獲物を探しています。
- ネズミ類:ドブネズミやクマネズミが主な獲物
- 小鳥:スズメやムクドリなどの都市鳥
- 人間の食べ残し:ゴミ箱漁りも得意
都市部のイタチは、人間の生活に適応して、意外なものも食べるんです。
一方、農村部のイタチさんはこんな感じ。
- 野ネズミ類:ハツカネズミやアカネズミが主食
- 小型哺乳類:モグラやリスも狙います
- 両生類や爬虫類:カエルやトカゲも大好物
- 昆虫類:コオロギやカブトムシの幼虫など
農村部のイタチは、自然の中で多様な獲物を狙います。
面白いのは、都市部のイタチが人間の食べ残しを利用する能力を身につけていること。
これは農村部のイタチにはあまり見られない特徴です。
「人間様、ごちそうさまです!」って感じですね。
でも、注意が必要なのは、都市部のイタチが人間の食べ物に慣れすぎてしまうこと。
自然の獲物を捕る能力が衰えてしまう可能性があるんです。
「便利な生活に慣れすぎちゃった!」というわけです。
このように、イタチの食性は環境に応じて柔軟に変化します。
都市部と農村部での違いを理解することで、それぞれの地域に適したイタチ対策を考えることができるんです。
春夏のイタチvs秋冬のイタチ!季節で変わる食性
イタチの食性は季節によってガラリと変わります。まるで、春夏と秋冬で別のイタチさんになっちゃうみたいですよ。
まずは、春夏のイタチさん。
こんな感じで食事をしています。
- 小型哺乳類:ネズミやモグラが大好物
- 鳥類の卵や雛:繁殖期の鳥の巣を狙います
- 昆虫類:甲虫やバッタなどの虫も食べます
春夏は動物性のタンパク質をたっぷり摂取するんです。
一方、秋冬のイタチさんはこんな感じ。
- 果実類:熟した果物や木の実を食べます
- 冬眠中の小動物:冬眠中のカエルやヘビを狙います
- 魚類:凍っていない水辺で魚を捕まえます
秋冬は植物性の食べ物の割合が増えます。
面白いのは、イタチが季節の変化に合わせて、自分の食性を柔軟に変えられること。
これは、イタチの生存戦略の一つなんです。
「季節に合わせて食べ物を変えないと、生き残れないもんね」というわけです。
春夏は、繁殖期に備えてタンパク質をたくさん摂取します。
「赤ちゃんのために栄養をつけなきゃ!」って感じですね。
一方、秋冬は、動物性の獲物が少なくなるので、果実類で栄養を補います。
「寒い冬を乗り越えるためには、バランスの良い食事が大切だよ」というところでしょう。
このようなイタチの季節による食性の変化を理解することで、時期に応じた効果的なイタチ対策を立てることができます。
例えば、春夏は小動物の侵入を防ぐ対策、秋冬は果樹園への侵入を防ぐ対策を重点的に行うといった具合です。
イタチが好む獲物vs避ける獲物!栄養価の違いに注目
イタチの食卓には、大好物と苦手な食べ物があるんです。その違いは、主に栄養価にあります。
イタチさんも、「美味しくて体にいいものを食べたい!」と思っているんですね。
まずは、イタチが好む獲物の特徴を見てみましょう。
- 高タンパク質:体の成長や維持に必要
- 適度な脂肪分:エネルギー源として重要
- ビタミン・ミネラル豊富:健康維持に欠かせない
- 捕まえやすいサイズ:自分の体重の半分以下が理想的
「今日のランチはネズミさん!」って喜んでいるかも。
ネズミは高タンパクで、適度な脂肪分があり、栄養バランスが良いんです。
一方、イタチが避ける獲物はこんな特徴があります。
- 繊維質が多い:消化が難しい
- 大型すぎる:捕まえるのが危険
- 毒を持つ:体に悪影響がある
- 栄養価が低い:食べても満腹感が得られない
捕まえようとしてケガをする可能性があるので、避けるんです。
面白いのは、イタチが栄養価の高い獲物を本能的に選んでいること。
「これ食べたら元気になれそう!」って感じで選んでいるんですね。
例えば、卵は栄養の宝庫。
イタチはそれを知っているかのように、巣を探して卵を食べます。
また、イタチは季節によって好む獲物を変えます。
春は栄養価の高い小動物、秋は果実類というように。
「季節の変わり目には、体調管理が大切だもんね」というわけです。
このようなイタチの食性の特徴を知ることで、効果的な対策を立てられます。
例えば、イタチの好む獲物を庭に置かないようにしたり、逆にイタチの苦手な植物を植えたりすることで、イタチの侵入を防ぐことができるんです。
山間部のイタチvs海岸部のイタチ!環境で変わる食性
イタチの食性は、住んでいる場所によってもガラリと変わります。山に住むイタチさんと海の近くに住むイタチさん、その食生活はまるで別物なんです。
まずは、山間部のイタチさん。
こんな感じのメニューです。
- リスやモモンガ:木の上を走り回る小動物が得意
- キジやヤマドリ:山野に生息する鳥類も狙います
- 山菜や木の実:植物性の食べ物も取り入れます
- 昆虫類:カブトムシやクワガタの幼虫など
山の豊かな自然の中で、多様な食材を楽しんでいるんです。
一方、海岸部のイタチさんはこんな感じ。
- 小魚や甲殻類:潮だまりで捕まえます
- 海鳥の卵:崖の上の巣を狙います
- 打ち上げられた海藻:栄養補給に利用
- 貝類:干潟で見つけた貝を食べます
海の幸をたっぷり利用した食生活を送っています。
面白いのは、それぞれの環境に合わせて、イタチが独自の狩猟技術を発達させていること。
山のイタチは木登りが上手で、海辺のイタチは泳ぎが得意だったりするんです。
「環境に合わせて、特技も変わるんだね」というわけです。
また、それぞれの環境特有の季節変化にも適応しています。
山のイタチは冬になると木の実や冬眠中の動物を多く食べるようになり、海辺のイタチは潮の満ち引きに合わせて狩りの時間を調整したりします。
「自然のリズムに合わせて生活するのが一番!」ってところでしょうか。
このように、イタチの食性は環境によって大きく変化します。
そのため、イタチ対策を考える際には、その地域の特性をよく理解することが大切。
山間部では木登り対策、海岸部では水辺からの侵入対策など、環境に応じた対策が効果的なんです。
イタチの被害対策!獲物の特徴を知って効果的な予防法を実践

イタチの好物を庭に放置するのは「逆効果」だった!
イタチの好物を庭に放置するのは、まるでイタチさんを招待しているようなものです。これ、実は逆効果なんです!
「えっ、そうなの?」って思いますよね。
でも、考えてみてください。
イタチさんにとって、おいしい食べ物がある場所って、まるで高級レストランのようなもの。
「ここなら美味しいごはんが食べられるぞ!」って、どんどん寄ってきちゃうんです。
イタチの好物リストをおさらいしてみましょう。
- 小型哺乳類:ネズミ、モグラなど
- 小鳥:スズメ、ウグイスなど
- 卵:鳥の卵や爬虫類の卵
- 果物:特に甘くて柔らかいもの
例えば、庭に鳥の餌台を置いているとしましょう。
「かわいい小鳥さんたちにごはんをあげよう」って良いことのつもりでも、イタチさんからすれば「美味しそうな小鳥がいっぱい集まってるぞ!」ってことなんです。
果物の木がある場合も要注意。
落ちた果実をそのまま放置していると、「甘くておいしい果物バー」になっちゃいます。
イタチさん、大喜びです。
じゃあ、どうすればいいの?
ここがポイントです。
- 小動物の餌付けは控えめに
- 落下した果実はすぐに片付ける
- ゴミは密閉して保管する
- 庭を清潔に保つ
「ここには美味しいものないや」って、イタチさんも諦めてどこかへ行っちゃいます。
イタチ対策の基本は、彼らの好物を知ること。
そして、その好物を置かないこと。
これで、イタチの被害はぐっと減りますよ。
賢い対策で、イタチさんとの平和な共存を目指しましょう!
イタチの嫌いな「匂い」で獲物を寄せ付けない環境作り
イタチさん、実はある匂いが大の苦手なんです。この匂いを利用すれば、イタチの獲物を寄せ付けない環境が作れちゃいます。
「えっ、匂いだけでイタチを追い払えるの?」って思いますよね。
でも、イタチさんの鼻はとっても敏感。
人間の100倍以上の嗅覚を持っているんです。
だから、私たちには何でもない匂いでも、イタチさんにとっては「うわっ、くさい!」ってなっちゃうんです。
では、イタチが嫌う匂いにはどんなものがあるでしょうか?
- 柑橘系の香り:レモン、オレンジ、ゆずなど
- ハーブの香り:ミント、ラベンダー、ローズマリーなど
- 香辛料の匂い:唐辛子、胡椒、わさびなど
- 化学的な匂い:アンモニア、漂白剤など
例えば、庭にミントやラベンダーを植えてみましょう。
「いい香りだな〜」って人間は喜びますが、イタチさんは「うっ、この匂い苦手〜」ってなっちゃいます。
柑橘系の果物の皮を乾燥させて、庭のあちこちに置くのも効果的。
「いい香り!」と思う人間と、「くさっ!」と思うイタチさんの温度差がすごいんです。
でも、注意点もあります。
- 強すぎる匂いは人間にも不快かも
- 雨や風で匂いが消えやすいので定期的な補充が必要
- 化学的な匂いは植物や他の動物にも影響があるかも
「ここは匂いが変だぞ」ってイタチさんが思えば、獲物も寄ってこなくなります。
結果的に、イタチの被害も減らせるんです。
匂いを使った対策、意外と簡単でしょう?
自然の力を借りて、イタチさんとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。
きっと、あなたの庭は人間にとっても、動物にとっても居心地の良い場所になりますよ。
光と音でイタチの獲物を追い払う!「複合的な対策」が鍵
光と音を使えば、イタチの獲物を効果的に追い払えるんです。しかも、これらを組み合わせた「複合的な対策」が、さらに効果的なんですよ。
「えっ、光と音だけでイタチの獲物が逃げちゃうの?」って思いますよね。
でも、小動物たちにとっては、突然の光や音は「危険信号」なんです。
「ヤバイ!捕食者が来た!」って思って逃げちゃうんです。
では、具体的にどんな光と音が効果的でしょうか?
- 光:強い白色光、点滅する光、動きのある光
- 音:高周波音、不規則な音、突然の大きな音
例えば、庭に動きセンサー付きのライトを設置してみましょう。
何か動くと「パッ」と明るくなるんです。
人間にとっては便利な防犯ライトですが、小動物たちには「うわっ、まぶしい!」って驚きの光なんです。
音の対策なら、高周波発生装置がおすすめ。
人間には聞こえにくい高い音を出すんですが、小動物たちには「キーン」ってうるさく聞こえちゃうんです。
でも、ここがポイント。
光や音を単独で使うより、組み合わせて使う方がずっと効果的なんです。
- 光と音を同時に使う
- 不規則なタイミングで作動させる
- 場所を変えて設置する
結果、イタチの獲物が減って、イタチも来なくなるというわけ。
ただし、注意点もあります。
- 近所迷惑にならないよう、音量や光の強さに気をつける
- ペットにも影響があるかもしれないので様子を見る
- 野生動物全般を追い払ってしまう可能性がある
「ここは落ち着かないな〜」ってイタチの獲物たちが思えば、イタチも自然と遠ざかっていきます。
光と音を味方につけて、イタチとの上手な付き合い方を見つけていきましょう。
きっと、あなたの庭は人間にとっても、動物にとっても、ちょうどいい距離感の場所になりますよ。
イタチの獲物の隠れ場所をなくす!「整理整頓」が大切
イタチの獲物たちが大好きな隠れ場所、実はあなたの庭にたくさんあるかもしれません。これをなくすことが、イタチ対策の重要なポイントなんです。
つまり、「整理整頓」が大切ってことなんですよ。
「えっ、掃除するだけでイタチ対策になるの?」って思いますよね。
でも、考えてみてください。
イタチの獲物たちにとって、安全な隠れ場所がなくなれば、そこに住み着くのは怖いですよね。
「ここは危険がいっぱい!」って思って、別の場所に引っ越しちゃうんです。
では、イタチの獲物たちが好む隠れ場所には、どんなものがあるでしょうか?
- 積み重ねた木材や枝:小動物の絶好の隠れ家に
- 放置された古タイヤ:中に雨水がたまって虫の breeding ground に
- 茂みや雑草:ネズミやトカゲの隠れ家に最適
- 壊れた道具や機械:小動物のアパートみたいなもの
具体的には、こんな「整理整頓」がおすすめです。
- 庭の隅に積んである木材や枝を片付ける
- 使っていない古タイヤは処分するか、立てて保管する
- 茂みや雑草は定期的に刈り込む
- 壊れた道具や機械は修理するか、処分する
- 物置は整理して、隙間をなくす
小動物たちにとっては、「あそこに逃げ込もう!」ってところがなくなるんです。
でも、ちょっと待って!
全部きれいにしすぎるのも考えものです。
- 自然な景観を完全になくさない
- 益虫の住処も考慮する
- 急激な環境変化は避ける
「ここは住みやすいけど、隠れ場所が少ないな〜」って小動物たちが思えば、イタチも自然と来なくなります。
「整理整頓」でイタチ対策、意外と簡単でしょう?
庭をきれいにすることで、人間にとっても気持ちの良い空間になりますし、イタチの被害も減らせる。
一石二鳥どころか、三鳥くらいの効果があるんです。
さあ、今日から少しずつ始めてみましょう!
イタチの天敵を利用?「自然の力」で被害を防ぐ方法
イタチにも天敵がいるんです。この「自然の力」を上手に利用すれば、イタチの被害を防ぐことができるんですよ。
「えっ、イタチにも天敵がいるの?」って驚くかもしれませんね。
でも、自然界では、食う食われるの関係が複雑に絡み合っているんです。
イタチだって例外じゃありません。
では、イタチの天敵にはどんな動物がいるのでしょうか?
- 大型の猛禽類:フクロウ、タカなど
- 大型の哺乳類:キツネ、タヌキなど
- 大型のヘビ:アオダイショウなど
「ヤバイ、ここは危険だぞ!」って思うわけです。
では、どうやってこの「自然の力」を利用すればいいのでしょうか?
具体的な方法を見てみましょう。
- フクロウの巣箱を設置する:フクロウが住み着けば、イタチも警戒します
- タカが止まれる高い木を植える:タカのカの姿が見えるだけで、イタチは警戒します
- キツネやタヌキが好む環境を作る:果樹を植えたり、小川を作ったりすると、彼らが来やすくなります
- ヘビが住みやすい環境を整える:石垣や岩場を作ると、ヘビが住み着きやすくなります
結果として、イタチの来訪を減らすことができるんです。
でも、ちょっと待って!
天敵を呼び込むのは、良いことばかりではありません。
- 新たな被害が発生する可能性がある
- 生態系のバランスが崩れる恐れがある
- 近所の人が怖がるかもしれない
それでも、「自然の力」を利用するのは、とってもエコな方法。
農薬や化学物質を使わずに、自然のバランスでイタチを遠ざけることができるんです。
「イタチの天敵を味方につける」なんて、ちょっとドキドキしますよね。
でも、これも立派なイタチ対策の一つ。
自然の仕組みを理解して、上手に活用することで、人間もイタチも、そして天敵たちも、みんなが共存できる環境が作れるかもしれません。
自然の力を借りたイタチ対策、あなたも試してみませんか?
きっと、新しい発見があるはずです。