イタチは何を食べる?【小動物中心、果物も】1日の必要カロリーと採餌行動の特徴を解説

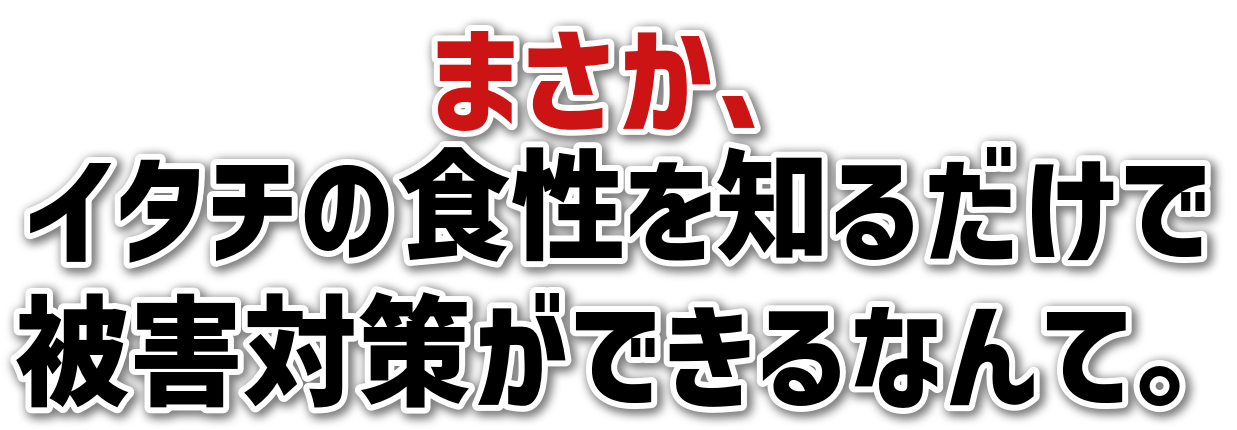
【この記事に書かれてあること】
イタチの食性を知ることは、効果的な被害対策の第一歩です。- イタチは雑食性で、動物性70%、植物性30%の食性
- ネズミやモグラなどの小動物が主食
- 意外にも果物や昆虫類も食べる
- 季節や地域によって食性が変化する
- イタチの食性を知ることで効果的な対策が可能に
意外にも、イタチは完全な肉食動物ではありません。
ネズミやモグラなどの小動物を主食としながら、果物や昆虫類も食べる雑食性の動物なんです。
食べ物の種類や割合を知れば、イタチ対策の幅が広がります。
季節や地域によって変化するイタチの食性。
その特徴を理解し、適切な対策を立てることで、イタチによる被害を最小限に抑えることができるんです。
さあ、イタチの食卓の秘密に迫ってみましょう!
【もくじ】
イタチは何を食べる?特徴と主な食べ物

イタチの食性は「肉食」ではなく「雑食性」だった!
意外かもしれませんが、イタチは完全な肉食動物ではありません。実は雑食性なんです。
「えっ、イタチって小動物を襲う肉食動物じゃないの?」と思った方も多いでしょう。
確かにイタチは小動物を主食としていますが、実は果物や植物も食べるんです。
イタチの食事内容は、およそ次のような割合になっています。
- 動物性の食べ物:70%
- 植物性の食べ物:30%
この雑食性という特徴は、イタチが様々な環境に適応できる理由の一つでもあります。
「でも、なんで雑食なの?」って思いますよね。
実はイタチは体が小さく、エネルギーを効率よく摂取する必要があるんです。
だから、季節や環境に応じて柔軟に食べ物を選ぶことができるようになったわけです。
イタチの雑食性を知ることで、効果的な対策が立てられます。
例えば、果物の木を守るのと同時に、小動物の住処も減らすなど、総合的なアプローチが可能になるんです。
イタチが好む小動物「ネズミ」「モグラ」「ウサギ」に注目
イタチの食事の主役は、やっぱり小動物です。特にネズミ、モグラ、ウサギが大好物なんです。
「ちょっと待って!ウサギってイタチより大きくない?」って思いましたか?
実はイタチ、体は小さいけど狩りの達人なんです。
イタチが好む小動物を見てみましょう。
- ネズミ:イタチの定番メニュー。
小回りが利くイタチにとって、絶好の獲物です。 - モグラ:地中にいても、イタチの鋭い嗅覚で見つけちゃいます。
- ウサギ:イタチより大きいけど、素早い動きで襲いかかります。
「シュッ」と素早く動き、「ガブッ」と獲物を捕らえる。
その姿は、小さな体からは想像できないほどの迫力があるんです。
ここで注目したいのは、これらの小動物が人間の生活環境にも多く生息しているということ。
つまり、イタチが人家の周りに現れるのは、好物の小動物を追いかけてきているからなんです。
「じゃあ、イタチ対策には小動物対策も必要ってこと?」そのとおりです。
イタチの好物を知ることで、より効果的な対策が立てられるんです。
例えば、ネズミ除けの対策をすることで、間接的にイタチも寄せ付けなくなる、というわけです。
意外と多い!イタチが食べる「果物」や「昆虫類」
イタチの食卓には、意外にも果物や昆虫類もよく並んでいます。「えっ、イタチが果物を?」と驚く方も多いでしょう。
でも、これが事実なんです。
イタチは意外と甘いものが好きで、特に熟した果実が大好物なんです。
イタチが好む果物や昆虫類を見てみましょう。
- 果物:ぶどう、いちご、さくらんぼなどの小型の果実
- 木の実:どんぐり、くるみ、まつぼっくりの種など
- 昆虫類:カブトムシ、コオロギ、バッタなどの大型昆虫
「モグモグ」と頬を膨らませて食べる姿は、まるでリスのよう。
でも、果樹園の方にとっては大問題です。
「ということは、果樹園や畑でイタチを見かけても不思議じゃないってこと?」そのとおりです。
特に果実の収穫期には要注意。
イタチは甘い匂いに誘われて、どんどん人里に近づいてくるんです。
昆虫類も重要な栄養源。
イタチは小回りの利く体を活かして、素早く昆虫を捕まえます。
「ガサガサ」と草むらを探り、「パクッ」と昆虫を捕まえる様子は、まるで宝探しをしているよう。
この多様な食性を知ることで、イタチ対策の幅が広がります。
例えば、果樹に反射テープを巻いたり、昆虫の住処を減らしたりすることで、イタチを寄せ付けにくくすることができるんです。
イタチの食事の70%は動物性!残り30%は植物性
イタチの食事内容、気になりますよね。実は、イタチの食事は動物性が70%、植物性が30%という割合なんです。
「へえ、思ったより植物性が多いんだ」と驚いた方も多いのではないでしょうか。
イタチの食事内容を詳しく見てみましょう。
- 動物性食物(70%):
- 小型哺乳類(ネズミ、モグラなど)
- 鳥類とその卵
- 魚類
- 昆虫類
- 植物性食物(30%):
- 果実(ぶどう、いちごなど)
- 木の実(どんぐり、くるみなど)
- 野草の葉や茎
「ガツガツ」と肉を食べつつ、「モグモグ」と果物も楽しむ。
まるで人間のような食生活です。
でも、なぜこんな割合なのでしょうか。
実は、イタチの体のつくりと深い関係があるんです。
イタチは消化管が短いため、栄養価の高い動物性タンパク質を多く必要とします。
一方で、植物性の食べ物は消化に時間がかかるため、少量で十分なんです。
「じゃあ、イタチ対策は動物性の餌を減らすことが重要ってこと?」その通りです。
でも、植物性の餌も忘れずに。
両方の対策をすることで、より効果的にイタチを寄せ付けなくすることができるんです。
イタチの食べ物を与えるのは要注意!被害を招く可能性も
イタチに食べ物を与えるのは、絶対にやめましょう。「かわいそうだから」とか「追い払えるかも」と思って餌付けしても、それが大きな間違いになる可能性があるんです。
イタチに餌を与えることで起こる問題を見てみましょう。
- イタチが人間を恐れなくなる
- イタチの数が増える
- 周辺の生態系のバランスが崩れる
- 家屋への侵入リスクが高まる
- 病気や寄生虫の感染リスクが上がる
実は、イタチに餌を与えることは、イタチにとっても人間にとっても良いことではないんです。
イタチは野生動物。
人間に餌をもらうことで、自然な警戒心を失ってしまいます。
「ガサガサ」と音がしても逃げない、「ヒョコヒョコ」と人前に現れる。
そんなイタチが増えれば、被害も増えてしまうんです。
また、餌付けによってイタチの数が増えすぎると、周辺の生態系にも影響が出ます。
イタチの天敵や獲物の数のバランスが崩れ、思わぬ被害を招く可能性があるんです。
「じゃあ、イタチを見かけても無視するのが一番?」そうですね。
イタチとの適切な距離感を保つことが、人間とイタチの共存には不可欠なんです。
餌付けせずに、自然な生態系の中でイタチが生きていけるよう、環境を整えることが大切です。
イタチの食性の変化と地域差を知ろう

春夏と秋冬で変わる!イタチの季節別食性の特徴
イタチの食べ物は、季節によってガラリと変わります。春夏はネズミなどの小動物中心、秋冬は果実や木の実の割合が増えるんです。
「えっ、イタチって季節で食べ物が変わるの?」と驚いた方も多いでしょう。
イタチの季節別食性を見てみましょう。
- 春夏:ネズミ、モグラ、小鳥などの小動物が中心
- 秋:果実や木の実の割合が増加
- 冬:貯蔵した食べ物や冬眠しない小動物が中心
「ピョンピョン」跳ねながら、小動物を追いかけ回します。
この時期はタンパク質豊富な食事で、子育ての準備をするんです。
秋になると、イタチの食卓はまるで果物屋さん。
「モグモグ」と果実を頬張る姿は、意外にもかわいらしいものです。
これは冬に備えて栄養を蓄えるためなんです。
冬は厳しい季節。
でも、イタチは賢いんです。
「ちょこちょこ」と動き回り、貯蔵した食べ物や冬眠しない小動物を探し出します。
まるで冷蔵庫から食べ物を取り出すみたい。
この季節による食性の変化を知ることで、効果的な対策が立てられます。
例えば、秋には果樹園の見回りを増やしたり、冬は貯蔵庫の管理を徹底したりするといった具合です。
イタチの食べ物カレンダーを把握して、一歩先を行く対策を心がけましょう。
都市部vs農村部!イタチの食べ物の違いとは
イタチの食べ物は、都市部と農村部でかなり違います。都市部では人間の食べ残しや小型ペットも食べることがあるんです。
一方、農村部では野生動物や農作物が主食。
「えっ、イタチって場所によって食べ物が全然違うの?」と驚くかもしれませんね。
都市部と農村部でのイタチの食べ物を比べてみましょう。
- 都市部:
- 人間の食べ残し(ゴミ箱荒らしの名人!
) - 小型ペット(注意が必要です)
- 都市に生息する小動物(ネズミ、小鳥など)
- 農村部:
- 野生の小動物(ネズミ、モグラ、ウサギなど)
- 農作物(果物、野菜)
- 昆虫類(カブトムシ、コオロギなど)
「ガサガサ」とゴミをあさり、人間の食べ残しを見つけては「パクパク」と食べています。
時には小型ペットも狙うので要注意。
「うちの猫ちゃんが危ない!」なんてことにならないよう、ペットの管理には気をつけましょう。
一方、農村部のイタチは自然の恵みをたっぷり享受。
「ピョンピョン」と野原を駆け回り、野生動物を追いかけます。
果樹園では「モグモグ」と果物を食べ、畑では「シャキシャキ」と野菜をかじります。
この違いを理解することで、環境に応じた対策が立てられます。
都市部ならゴミの管理を徹底し、農村部なら農作物の保護に力を入れるといった具合です。
イタチの食べ物マップを頭に描いて、効果的な対策を考えてみましょう。
海辺のイタチと山のイタチ!食べ物の違いに驚き
イタチの食べ物は、海辺と山でも大きく違います。海辺のイタチは魚や貝類も食べるんです。
一方、山のイタチは野生動物や山の果実が主食。
「えっ、イタチって泳げるの?山に登れるの?」と驚く方も多いでしょう。
海辺と山のイタチの食べ物を見比べてみましょう。
- 海辺のイタチ:
- 魚類(小魚が主な獲物)
- 甲殻類(カニやエビ)
- 貝類(小さな巻貝など)
- 山のイタチ:
- 野生の小動物(ネズミ、リス、モモンガなど)
- 山の果実(木イチゴ、ブルーベリーなど)
- キノコ類
「ザブザブ」と水に入り、素早い動きで魚を捕まえます。
「パクッ」とカニをつかんだり、「コリコリ」と貝を食べたり。
その姿は意外にもかわいらしいものです。
一方、山のイタチは森の冒険家。
「サササッ」と木々の間を駆け抜け、小動物を追いかけます。
「モグモグ」と山の果実を頬張る姿は、まるでピクニックを楽しんでいるよう。
時には「クンクン」と匂いを嗅ぎ、キノコを探すことも。
この違いを知ることで、環境に合わせた対策が立てられます。
海辺なら魚の残骸の管理を、山なら果樹園の保護を重視するといった具合です。
イタチの食べ物地図を頭に描いて、効果的な対策を考えてみましょう。
自然豊かな場所ほど、イタチとの共存を考える必要があるんです。
繁殖期に変化!イタチの食性と栄養摂取の関係
イタチの食べ物は、繁殖期になるとガラリと変わります。この時期、イタチはタンパク質や脂肪分の多い小動物を積極的に捕食するんです。
「えっ、イタチも赤ちゃんのために栄養に気をつけるの?」と驚く方も多いでしょう。
繁殖期のイタチの食事内容を見てみましょう。
- タンパク質豊富な小動物(ネズミ、モグラ、小鳥など)
- 脂肪分の多い獲物(小型の哺乳類)
- 栄養価の高い卵(鳥の卵)
- カルシウム源(小魚の骨など)
「ガツガツ」とタンパク質豊富な小動物を食べ、「パクパク」と脂肪分の多い獲物を捕まえます。
時には「コトコト」と鳥の巣を探し回り、栄養満点の卵を見つけることも。
この時期、イタチのお母さんは子育てに備えて特に栄養を必要とします。
まるで妊婦さんのように、バランスの取れた食事を心がけているんです。
「うーん、どうやって栄養のある食べ物を見つけるんだろう?」と不思議に思うかもしれません。
実は、イタチは優れた嗅覚と聴覚を使って、栄養価の高い獲物を探し当てるんです。
この繁殖期の食性変化を理解することで、より効果的な対策が立てられます。
例えば、繁殖期には家禽類の管理を特に徹底するとか、栄養価の高い小動物の生息地を整備するといった具合です。
イタチの「食べ物カレンダー」に繁殖期の特徴を書き込んで、一年を通じた対策を考えてみましょう。
イタチとの上手な付き合い方が見えてくるはずです。
イタチの食性を知って効果的な対策を

イタチの好物を知って「餌付け」を避ける!被害予防のコツ
イタチの好物を知ることは、効果的な被害予防の第一歩です。でも、その知識を使って餌付けをするのは絶対にダメ!
かえって被害を招いてしまうんです。
「えっ、餌付けしちゃダメなの?」と思った方も多いでしょう。
実は、イタチに餌を与えることで、次のような問題が起こる可能性があるんです。
- イタチが人を恐れなくなる
- イタチの数が増える
- 周辺の生態系のバランスが崩れる
- 家屋への侵入リスクが高まる
そうなると、「ガサガサ」「ドタドタ」と庭を荒らしたり、「ガリガリ」と家の中に侵入しようとしたりする可能性が高くなるんです。
じゃあ、どうすればいいの?
イタチの好物を知ったら、それを家の周りから遠ざけることが大切です。
例えば、ネズミやモグラが好きなイタチには、これらの小動物が寄り付かない環境づくりをしましょう。
具体的には、次のような対策が効果的です。
- ゴミ箱はしっかり蓋をする
- 落ち葉や枯れ枝を片付ける
- 果樹の実は早めに収穫する
- 餌になりそうな小動物を寄せ付けない環境を作る
そうすれば、イタチは自然と別の場所へ移動していくでしょう。
イタチの好物を知ることは大切。
でも、それを与えるのではなく、遠ざけることが被害予防のコツなんです。
「なるほど、そういうことか!」と納得していただけましたか?
イタチの嫌いな「柑橘系の香り」を活用!自然な忌避策
イタチは意外にも、柑橘系の香りが大の苦手なんです。この特徴を利用すれば、自然な方法でイタチを寄せ付けない環境を作ることができます。
「えっ、イタチってレモンの匂いが嫌いなの?」と驚いた方も多いでしょう。
実は、イタチの鼻はとっても敏感。
人間の100倍以上の嗅覚を持っているんです。
だから、私たちには心地よい柑橘系の香りも、イタチにとっては強烈な刺激になってしまうんですね。
では、具体的にどんな柑橘系の香りを使えばいいのでしょうか?
- レモン
- オレンジ
- みかん
- ゆず
- ライム
「ポイポイ」と適当に置くだけでも効果がありますが、「シュルシュル」と糸に通して、風に揺れるようにすると、より効果的です。
「でも、果物の皮って腐っちゃわない?」そんな心配も不要です。
乾燥させた皮は長持ちしますし、腐る前に交換すれば問題ありません。
他にも、柑橘系のエッセンシャルオイルを使う方法もあります。
綿棒に数滴垂らして、イタチの侵入しそうな場所に置いてみてください。
「スーッ」と広がる香りで、イタチは「ピュー」と逃げ出してしまうかもしれませんよ。
この方法の良いところは、人や環境にやさしいということ。
化学物質を使わないので、お子さんやペットがいる家庭でも安心して使えます。
ただし、注意点もあります。
柑橘系の香りは強すぎると、人間も不快に感じる可能性があります。
適度な量を使うことを心がけましょう。
イタチの嫌いな柑橘系の香りを上手に活用すれば、自然な方法でイタチ対策ができるんです。
「よし、今度の週末にやってみよう!」そんな気持ちになりましたか?
庭に「砂場」を作ってイタチの餌を遠ざける驚きの方法
意外かもしれませんが、庭に砂場を作ることで、イタチの餌を遠ざけることができるんです。「えっ、砂場?子どもの遊び場じゃないの?」と思った方も多いでしょう。
実は、この方法、とっても効果的なんですよ。
なぜ砂場がイタチ対策になるのか、その理由を見てみましょう。
- イタチの主食であるネズミやモグラが砂地を嫌う
- 砂は水はけが良く、虫が住みにくい
- 砂場の周りは開けた空間になり、小動物が警戒する
これって、まるで魔法みたいですよね。
では、具体的にどんな砂場を作ればいいのでしょうか?
- 大きさ:最低でも2m×2m程度
- 深さ:30cm以上
- 砂の種類:川砂や海砂(ゴミや雑草の種が少ない)
- 周囲:木や石で囲むと◎
庭全体を砂利で覆うのも効果的です。
「サクサク」と歩く音が小動物を警戒させるんですね。
砂場を作る際は、周囲の環境にも気を配りましょう。
例えば、砂場の周りに「カサカサ」と音がする植物を植えると、小動物がさらに警戒するようになります。
また、「キラキラ」と光る風車を立てると、視覚的にも小動物を寄せ付けなくなります。
この方法の素晴らしいところは、イタチ対策になるだけでなく、お子さんの遊び場にもなること。
「一石二鳥」とはまさにこのことですね。
ただし、注意点もあります。
砂場は定期的に手入れが必要です。
「サラサラ」とした状態を保つために、時々砂をかき混ぜたり、新しい砂を足したりしましょう。
砂場作りで、イタチの餌を遠ざける。
意外な方法ですが、試してみる価値は十分にありそうですね。
「よし、今度の休みに砂場作りにチャレンジしてみよう!」そんな気持ちになりませんか?
「風車」や「反射テープ」でイタチを寄せつけない環境づくり
風車や反射テープを使って、イタチを寄せ付けない環境を作ることができるんです。「えっ、そんな簡単なもので効果があるの?」と驚く方も多いでしょう。
でも、これがなかなか効果的なんですよ。
イタチは警戒心が強い動物です。
突然の動きや光の変化に敏感に反応します。
この特性を利用して、イタチを寄せ付けない環境を作るのが、この方法のポイントです。
では、具体的にどんな使い方があるのでしょうか?
- 風車:庭や畑の周りに設置
- 反射テープ:果樹や柵に巻きつける
- 風鈴:軒下や木の枝に吊るす
- ペットボトル風車:手作りで庭に設置
反射テープは「キラキラ」と光って目をくらませ、風鈴は「チリンチリン」と音を立ててイタチを警戒させるんです。
特におすすめなのが、ペットボトルで作る手作り風車。
作り方は簡単です。
- ペットボトルを半分に切る
- 下半分に切れ込みを入れて羽根を作る
- 上半分を逆さまにして下半分にはめ込む
- 棒を差し込んで完成!
反射テープは果樹園での被害防止に特に効果的。
幹に巻きつけたり、枝から吊るしたりすると、「ピカピカ」と光ってイタチを怖がらせます。
この方法の良いところは、環境にやさしく、費用もあまりかからないこと。
家にある材料で簡単に作れるものばかりです。
ただし、注意点もあります。
風車や反射テープは定期的に点検が必要です。
風で飛ばされたり、劣化したりする可能性があるので、時々チェックしましょう。
風車や反射テープで、イタチを寄せ付けない環境づくり。
意外と簡単にできそうですね。
「よし、今週末にでも試してみよう!」そんな気持ちになりませんか?
イタチの食性を利用!効果的な「トラップ」の選び方
イタチの食性を知ることで、効果的なトラップを選ぶことができます。でも、ここで言う「トラップ」は捕獲用ではありません。
イタチを人道的に追い払うためのものなんです。
「えっ、捕まえないの?」と思った方もいるでしょう。
実は、捕獲よりも追い払いの方が長期的には効果的なんです。
では、イタチの食性を利用したトラップにはどんなものがあるでしょうか?
- 音声トラップ:イタチの天敵の鳴き声を再生
- 光トラップ:突然の強い光でイタチを驚かせる
- 匂いトラップ:イタチの嫌いな香りを利用
- 振動トラップ:地面の振動でイタチを警戒させる
イタチはこれらの動物を天敵と認識するので、その場から離れようとするんです。
光トラップは、人感センサーと強力なライトを組み合わせたもの。
イタチが近づくと「パッ」と強い光が当たり、イタチは「ビックリ」して逃げ出します。
匂いトラップは、先ほど紹介した柑橘系の香りを利用します。
「スーッ」と香りが広がる装置を設置すれば、イタチは近づかなくなります。
振動トラップは、地面に設置して振動を起こす装置です。
イタチが近づくと「ブルブル」と地面が振動し、イタチは危険を感じて逃げ出すんです。
これらのトラップを選ぶ際は、次のポイントを押さえましょう。
- 設置場所:イタチの侵入経路を把握する
- 効果の持続性:電池式なら交換時期に注意
- 周囲への影響:近隣の迷惑にならないか確認
- 季節性:イタチの活動が活発な時期に合わせる
「ここをよく通るな」という場所に集中して設置すると、効果が高まります。
ただし、これらのトラップに頼りすぎるのは禁物。
イタチは賢い動物なので、同じ方法を続けていると慣れてしまう可能性があります。
定期的に方法を変えるのがコツです。
イタチの食性を利用したトラップ選びは、イタチを人道的に追い払う効果的な方法です。
でも、これだけに頼らず、他の対策と組み合わせることが大切。
「よし、うちの庭に合うトラップを選んでみよう!」そんな気持ちになりませんか?
環境にも優しく、イタチとの共存を図る素晴らしい方法なんです。