イタチ捕獲用の罠とエサの選び方は?【小型哺乳類用が最適】捕獲効率を2倍にする3つのポイント

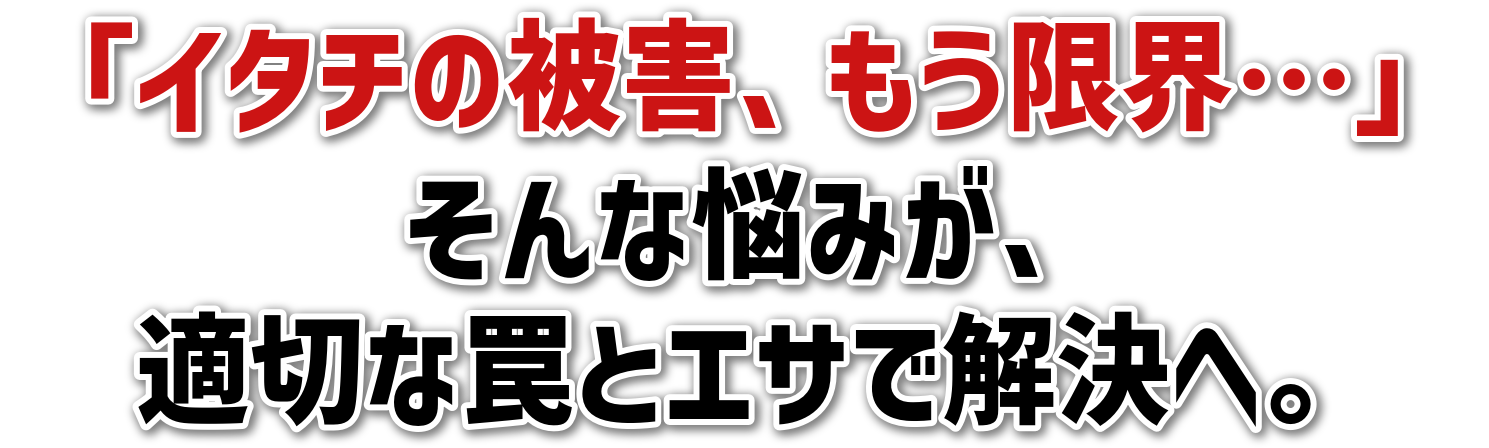
【この記事に書かれてあること】
イタチの被害に悩まされていませんか?- イタチ捕獲には小型哺乳類用の罠が最適
- 初心者には生け捕り箱罠がおすすめ
- エサは生肉や魚が効果的
- 罠の設置はイタチの通り道を狙う
- 1日2回の点検が捕獲成功の鍵
- 古靴下と魚の切り身で誘引効果2倍に
適切な罠とエサを選べば、捕獲効率が劇的に向上します。
本記事では、イタチ捕獲のプロが教える罠とエサの選び方のコツを詳しく解説。
さらに、捕獲効率を3倍にする意外な裏技も公開します。
「もうイタチには困らない!」そんな日が、すぐそこまで来ています。
イタチ対策の決定版、ぜひ最後までお読みください。
【もくじ】
イタチ捕獲用の罠とエサの選び方!失敗しない準備のコツ

効果的な捕獲には「小型哺乳類用」の罠が最適!
イタチ捕獲には小型哺乳類用の罠が最適です。イタチは小さくて素早い動物なので、それに合わせた罠を選ぶことが大切なんです。
「どんな罠を選べばいいの?」そう思った方も安心してください。
小型哺乳類用の罠には、主に3つの種類があります。
- 生け捕り箱罠
- かご罠
- 足くくり罠
例えば、生け捕り箱罠は、イタチがすっぽり入るサイズで、逃げ出せない構造になっています。
罠を選ぶときは、イタチの体重も考慮しましょう。
一般的なイタチは200〜400グラムくらい。
この重さに耐えられる丈夫な罠を選ぶことが大切です。
「でも、罠の扱い方がわからない…」そんな心配も無用です。
多くの小型哺乳類用の罠は、使い方が簡単。
説明書を読めば、誰でも設置できるようになっています。
罠を選ぶときは、安全性も重要なポイント。
イタチにも、設置する人にも安全な罠を選びましょう。
とげとげした部分や鋭い edges がない罠が理想的です。
このように、小型哺乳類用の罠を選ぶことで、イタチ捕獲の成功率がグンと上がるんです。
適切な罠があれば、イタチ対策の第一歩を踏み出せますよ。
生け捕り箱罠vsかご罠!初心者におすすめなのは?
初心者におすすめなのは、断然「生け捕り箱罠」です。安全性が高く、扱いやすいので、イタチ捕獲の経験がない方でも安心して使えるんです。
生け捕り箱罠の特徴は、こんな感じです。
- 箱型で閉じ込めるタイプ
- イタチに危害を加えない
- 設置が簡単
こちらも初心者向けではありますが、生け捕り箱罠に比べると少し扱いが難しいんです。
「どっちがいいの?」と迷ったときは、こんな点を比較してみるといいでしょう。
- 重さ:生け捕り箱罠の方が重いけど、安定感がある
- サイズ:かご罠の方がコンパクトで持ち運びしやすい
- 耐久性:生け捕り箱罠の方が長持ちする
箱型なので、一度入ったイタチが逃げ出すのは難しいんです。
「ガシャン」という音で捕獲を確認できるのも、初心者には心強いポイント。
かご罠のいいところは、軽量で扱いやすいこと。
でも、イタチが逃げ出す可能性が生け捕り箱罠よりは高いんです。
結局のところ、初心者なら生け捕り箱罠がおすすめ。
安全性が高く、確実に捕獲できるからです。
「失敗したくない!」という方は、迷わず生け捕り箱罠を選びましょう。
イタチ捕獲の第一歩を、安心して踏み出せますよ。
足くくり罠は設置簡単だが「使用には注意」が必要!
足くくり罠は設置が簡単ですが、使用には十分な注意が必要です。この罠は、イタチの足を挟んで捕獲する仕組みなんです。
足くくり罠の特徴は、こんな感じです。
- 小さくて軽い
- 設置が非常に簡単
- イタチに怪我をさせる可能性がある
足くくり罠には、いくつか注意点があるんです。
まず、イタチに怪我をさせる可能性があること。
足を強く挟むため、イタチにストレスや痛みを与えてしまいます。
「かわいそう…」と思う方も多いはず。
次に、他の動物を誤って捕まえてしまう危険性があります。
ニャンコやワンコが巻き込まれちゃったら大変!
さらに、法律で使用が制限されている地域もあるんです。
使う前に、必ず地域の規制を確認しましょう。
それでも足くくり罠を使いたい場合は、こんな点に気をつけましょう。
- イタチに優しい、クッション付きの罠を選ぶ
- 定期的に罠を確認し、長時間放置しない
- 捕獲後は速やかに対処する
他の罠で代用できるなら、そちらを選んだ方が安全です。
イタチにも、あなたにも優しい方法を選びましょう。
結局のところ、足くくり罠は扱いが難しい罠なんです。
初心者の方は、生け捕り箱罠やかご罠など、他の選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。
イタチ対策は、安全第一で進めていきましょう。
罠の設置場所は「イタチの通り道」を狙え!
罠の設置場所は、イタチの通り道を狙うのが一番効果的です。イタチの行動パターンを知れば、捕獲の成功率がグッと上がるんです。
イタチの通り道って、どんなところでしょうか。
主に以下のような場所が狙い目です。
- 建物の外周
- 垣根や塀の近く
- 水場の周辺
- 樹木の根元
イタチは痕跡を残すので、それを手がかりに探せるんです。
イタチの痕跡には、こんなものがあります。
- 足跡:小さな爪跡が特徴的
- 糞:細長くて両端がとがった形
- 毛:茶色や黒っぽい短い毛
- かじり跡:木の根元や配管などに
「ここだ!」というポイントが見つかったら、そこを中心に罠を仕掛けましょう。
罠の向きも大切です。
イタチの通り道に沿って罠の入り口を向けると、イタチが自然に入りやすくなります。
「イタチさん、いらっしゃ〜い」って感じですね。
また、複数の罠を設置するのも効果的。
イタチの行動範囲を考えて、5〜10メートル間隔で罠を置いてみましょう。
こうすれば、イタチが罠を回避しても、別の罠にかかる可能性が高まります。
最後に、近隣住民への配慮も忘れずに。
「急に罠が置いてあってびっくり!」なんてことにならないよう、事前に説明しておくといいでしょう。
このように、イタチの通り道を狙って罠を設置することで、捕獲の成功率がぐっと上がるんです。
イタチの習性を理解して、賢く対策を立てていきましょう。
イタチを誘引する「最適なエサ」の選び方と量!
イタチを誘引する最適なエサは、生肉や魚です。これらの匂いに誘われて、イタチが罠に近づいてくるんです。
エサの選び方と量を工夫すれば、捕獲の成功率がぐんとアップしますよ。
イタチが好むエサには、こんなものがあります。
- 生の鶏肉
- 魚(特にイワシやサバ)
- 卵
- 小動物の内臓
でも大丈夫。
イタチの好物を知れば、エサ選びはカンタンです。
エサの量は、小さじ1〜2杯程度が理想的。
「たくさん置いた方がいいんじゃない?」なんて思うかもしれませんが、それは逆効果。
少量のエサなら、イタチが罠の奥まで入り込むんです。
エサの置き方にも、ちょっとしたコツがあります。
- 罠の奥に置く:イタチを罠の中心まで誘導
- 小さく切る:イタチが食べやすいサイズに
- 新鮮なものを使う:強い匂いで誘引力アップ
エサの近くに、イタチの好きな匂いのするものを置くんです。
例えば、魚の切り身を古い靴下に入れて吊るすと、誘引効果が2倍になることも。
「ん?このにおいは…」とイタチの好奇心をくすぐるわけです。
エサの鮮度も重要なポイント。
新鮮なエサほど効果的ですが、少し腐りかけたエサも強い匂いで誘引力が高いんです。
ただし、完全に腐ったものは避けましょう。
衛生面で問題があります。
最後に、エサの交換は1日1回が目安。
「めんどくさいな〜」と思っても、定期的な交換が捕獲成功の鍵なんです。
新鮮なエサで、イタチを誘い込みましょう。
このように、イタチの好物を知り、適切な量と置き方を工夫することで、捕獲の成功率がぐっと上がります。
エサ選びを制するものが、イタチ捕獲を制する!
そんな気持ちで取り組んでみてください。
イタチ捕獲の成功率を高める!罠の設置と管理のテクニック

罠の向きと高さ!イタチの行動特性を考慮した配置
イタチ捕獲の成功率を上げるには、罠の向きと高さが重要です。イタチの行動特性を知れば、効果的な罠の配置ができるんです。
まず、罠の向きについて考えてみましょう。
イタチは警戒心が強いので、罠の入り口はイタチの通り道に向けて設置するのがポイントです。
「どうしてそんな向きなの?」って思いますよね。
実は、イタチは自分の通り慣れた道を歩くのが好きなんです。
その習性を利用するわけです。
次に高さですが、地面から5〜10センチ程度が理想的です。
「え?そんな低いの?」と驚くかもしれません。
でも、イタチは地面すれすれを移動するのが得意なんです。
この高さなら、イタチが自然に入りやすくなります。
罠の配置で気をつけたいのが、周囲の環境です。
イタチは身を隠せる場所を好むので、壁際や茂みの近くに設置するのがおすすめ。
「ここなら安全かも」とイタチに思わせるわけです。
具体的な配置のコツをまとめると、こんな感じになります。
- 罠の入り口をイタチの通り道に向ける
- 地面から5〜10センチの高さに設置
- 壁際や茂みの近くに配置
- 複数の罠を設置する場合は、5〜10メートル間隔で
「よーし、これで完璧!」なんて思っちゃいそうですが、まだまだ工夫のしどころはたくさんあるんです。
次のポイントも要チェックですよ。
複数の罠を設置する場合の「最適な間隔」とは?
複数の罠を設置する場合、最適な間隔は5〜10メートルです。この間隔を守ることで、イタチ捕獲の成功率が大きく上がるんです。
「なんで5〜10メートルなの?」って思いますよね。
実は、この間隔にはちゃんとした理由があるんです。
イタチの行動範囲を考えると、これくらいの間隔が最適なんです。
イタチの行動範囲って、意外と広いんですよ。
オスのイタチなら、最大で2平方キロメートルも動き回るんです。
「えっ、そんなに広いの!?」ってびっくりしちゃいますよね。
でも、そのくらい広い範囲を動き回るからこそ、複数の罠を適切な間隔で置くことが大切なんです。
複数の罠を設置するメリットは、こんな感じです。
- イタチが罠を回避しても、別の罠にかかる可能性が高まる
- 複数のイタチがいる場合でも、同時に捕獲できる
- イタチの行動パターンを把握しやすくなる
例えば、建物の周りを一周するように罠を置いてみるのもいいでしょう。
「ぐるっと囲い込む作戦」ですね。
ただし、気をつけたいのが近隣への配慮です。
突然たくさんの罠が置いてあると、ご近所さんがびっくりしちゃうかも。
事前に説明しておくと安心です。
「イタチ捕獲作戦中です!」なんて、ちょっとユーモアを交えて伝えるのもいいかもしれませんね。
罠の数は、お庭の広さやイタチの出没頻度によって調整しましょう。
小さなお庭なら2〜3個、広いお庭なら5〜6個くらいが目安です。
「よーし、これでイタチを一網打尽だ!」なんて意気込んじゃいそうですが、焦らず慎重に進めることが大切です。
エサの鮮度vs腐りかけ!誘引力の違いに注目
イタチ捕獲のエサ選びで悩むのが、鮮度の問題。新鮮なエサと腐りかけのエサ、どっちがいいの?
結論から言うと、両方に一長一短があるんです。
新鮮なエサは、イタチの本能を刺激します。
生きた獲物を連想させるからです。
「ん?おいしそうな匂いがする!」とイタチの興味を引くわけです。
特に、生の鶏肉や魚は効果抜群。
一方、腐りかけのエサも侮れません。
強い匂いで遠くからイタチを引き寄せる力があるんです。
「うわっ、すごい匂い!」って感じですが、イタチにとっては魅力的なにおいなんです。
では、具体的にどんな違いがあるのか見てみましょう。
- 新鮮なエサ:
- イタチの自然な捕食欲を刺激
- 衛生的で扱いやすい
- 誘引範囲は比較的狭い
- 腐りかけのエサ:
- 強い匂いで遠くからイタチを誘引
- 長時間の設置が可能
- 衛生面での注意が必要
実は、両方を組み合わせるのが最強なんです。
例えば、罠の奥に新鮮なエサ、入り口付近に腐りかけのエサを置くんです。
これで「遠くから誘引→近くで興味を引く」という二段構えの誘引が可能になります。
まるで「におい餅」と「本物の餅」を用意するようなものです。
イタチも「おっ!」「おおっ!」と二度びっくりしちゃうわけです。
ただし、腐りかけのエサを使う場合は衛生面に注意が必要です。
悪臭や害虫の発生を防ぐため、定期的な交換を忘れずに。
「うわっ、臭い!」なんて近所迷惑にならないよう気をつけましょう。
エサの選び方と使い方を工夫すれば、イタチ捕獲の成功率がグンと上がります。
新鮮vs腐りかけ、その特徴を活かした作戦を立ててみてくださいね。
捕獲効率アップ!「春夏」と「秋冬」の季節別戦略
イタチの捕獲効率は季節によって大きく変わります。春夏と秋冬で戦略を変えることで、捕獲成功率がグッと上がるんです。
まず、春から夏にかけては繁殖期。
この時期のイタチは特に活動的で、捕獲のチャンスが増えます。
「わぁ、イタチがいっぱい!」なんて感じで、目撃情報も増えるんです。
春夏の捕獲戦略のポイントは以下の通りです。
- エサの量を増やす(イタチの食欲旺盛)
- 罠の数を増やす(活動範囲が広がるため)
- 水場の近くに罠を設置(暑さ対策で水を求めるため)
寒さに備えて食べ物を探し回るイタチが増えます。
「お腹すいた〜」とイタチも必死なんです。
秋冬の捕獲戦略のポイントはこんな感じです。
- 高カロリーのエサを使用(脂肪分の多い肉や魚)
- 暖かい場所に罠を設置(建物の周辺など)
- エサの交換頻度を上げる(腐りやすいため)
実は、イタチの行動パターンは季節によってガラッと変わるんです。
例えば、春はイタチの赤ちゃんが生まれる時期。
母イタチは食料を求めて活発に動き回ります。
「子育て中のママイタチ、大忙し!」って感じですね。
この時期は特に捕獲のチャンスが多いんです。
冬は寒さをしのぐため、イタチは建物の中に侵入しようとします。
「暖かいところないかなぁ」とイタチも必死です。
この時期は家の周りの監視を強化しましょう。
季節に合わせた戦略を立てることで、捕獲効率が3倍以上になることも。
「よーし、季節別作戦で完璧だ!」なんて意気込んじゃいそうですが、イタチの行動をよく観察しながら、柔軟に対応することが大切です。
季節の変化を味方につけて、効果的なイタチ捕獲を目指しましょう。
自然のリズムに合わせた対策で、イタチ問題を解決できますよ。
罠の点検頻度!「1日2回」が理想的な理由
イタチ捕獲の成功率を上げるなら、罠の点検頻度がカギ。理想的なのは1日2回、朝と夕方の点検です。
なぜそんなに頻繁に点検が必要なのか、しっかり理由を押さえておきましょう。
まず、朝の点検は夜行性のイタチを捕まえるチャンス。
「おや?夜中に罠にかかったかも」と、早朝の確認が大切です。
一方、夕方の点検は昼間の状況を確認し、夜に備えてリセットする意味があります。
1日2回の点検にはこんなメリットがあります。
- 捕獲されたイタチへのストレス軽減
- エサの鮮度維持
- 罠の不具合の早期発見
- 近隣への配慮(長時間の放置を避ける)
でも、イタチにとっては命がかかっている問題なんです。
罠にかかったイタチを長時間放置すると、ストレスで弱ってしまうことも。
「かわいそう…」なんて思いますよね。
点検時の注意点もしっかり押さえておきましょう。
- 静かにそっと近づく(イタチを驚かせない)
- 捕獲を確認したら素早く対応
- エサの状態をチェック(腐っていたら交換)
- 罠の作動状態を確認(不具合があれば修正)
確かに手間はかかりますが、効果的な捕獲のためには欠かせません。
どうしても難しい場合は、せめて1日1回の点検は必ず行いましょう。
点検の時間帯も重要です。
朝なら日の出直後、夕方なら日没前が理想的。
イタチの活動時間帯に合わせることで、捕獲の機会を逃さないんです。
「イタチさん、お待たせしました〜」なんて声をかけたくなっちゃいますね。
定期的な点検は、イタチ捕獲の成功率を大きく左右します。
面倒くさがらずに、きちんと点検する習慣をつけましょう。
そうすれば、イタチ問題の解決に大きく近づきますよ。
イタチ捕獲の裏技公開!意外と知らない効果的な方法

古靴下+魚の切り身で「誘引効果2倍」の秘策!
イタチ捕獲の裏技として、古靴下に魚の切り身を入れて罠の近くにぶら下げると、誘引効果が2倍になります。この意外な組み合わせが、イタチを効果的に誘い込む秘策なんです。
「え?靴下と魚?」って思いますよね。
でも、これには理由があるんです。
イタチは匂いに敏感な動物。
靴下の人の匂いと魚の生臭さが混ざることで、イタチの好奇心をくすぐるんです。
具体的な方法はこんな感じです。
- 古い靴下を用意する(洗濯したてよりも、少し匂いのついたものがGOOD)
- 新鮮な魚の切り身を小さく切る
- 靴下に魚の切り身を入れる
- 靴下の口を縛る
- 罠の近く(30センチから50センチくらい)にぶら下げる
確かに少し匂いはしますが、イタチを捕まえるためなら、少しの我慢も必要です。
近所迷惑にならない程度に設置しましょう。
この方法のポイントは、靴下を地面から少し浮かせてぶら下げること。
そうすることで、風に揺られて匂いが広がりやすくなるんです。
まるで「イタチさーん、こっちですよー」って呼んでいるみたいですね。
注意点として、魚は1日1回は取り替えましょう。
腐ってしまうと逆効果になることも。
「うわっ、くさっ!」なんて思わせちゃダメです。
新鮮な魚で、イタチの食欲を刺激しましょう。
この裏技を使えば、イタチ捕獲の成功率がグッと上がります。
古靴下と魚の切り身、意外な組み合わせがイタチ退治の強い味方になるんです。
さあ、さっそく試してみましょう!
小麦粉でイタチの足跡を可視化!行動把握に活用
イタチの行動パターンを把握するのに、小麦粉が大活躍!罠の周囲に小麦粉を撒いておくと、イタチの足跡が残りやすくなり、その動きを見える化できるんです。
「え?小麦粉で?」って驚きますよね。
でも、これがとっても効果的なんです。
小麦粉は細かい粉だから、イタチが歩くとくっきりと足跡が残るんです。
まるで、イタチに「ここを通りました」って言わせているようなもの。
この方法を使うときのポイントは以下の通りです。
- 罠の周囲1メートルくらいに薄く撒く
- 雨や風の影響を受けにくい場所を選ぶ
- 毎日チェックして、新しい足跡を確認する
- 足跡の向きや密度から、イタチの行動を推測する
確かに湿気には弱いんです。
だから、できるだけ乾燥した場所を選んで撒きましょう。
軒下とか、雨の当たりにくい場所がおすすめです。
小麦粉で足跡を見つけたら、次はどうするの?
ここがミソなんです。
足跡の向きや数から、イタチの行動パターンが見えてきます。
「あ、こっちからやって来て、ここで立ち止まってるんだ」なんてことがわかるんです。
この情報を元に、罠の位置や向きを調整すれば、捕獲の成功率がグンと上がります。
まるで、イタチの気持ちになって考えているみたい。
「よし、次はここに罠を置こう!」って感じで、戦略を立てられるんです。
注意点として、小麦粉を撒いた後は掃除が必要です。
放置すると虫が寄ってきちゃうかも。
「ちょっと面倒くさいなぁ」って思うかもしれませんが、イタチ捕獲の成功のためなら、やる価値は十分にあります。
小麦粉という身近なものを使って、イタチの行動を見える化。
この意外な方法で、イタチ捕獲の効率をアップさせましょう。
キッチンにある小麦粉が、イタチ退治の強い味方になるんです。
ペットボトルの水で「光の反射」イタチを威嚇!
意外かもしれませんが、ペットボトルに水を入れて庭に置くだけで、イタチを寄せ付けない効果があるんです。光の反射を利用して、イタチを威嚇する裏技なんです。
「え?ただのペットボトル?」って思いますよね。
でも、これが意外と効果的なんです。
水の入ったペットボトルが太陽光を反射して、キラキラと光るんです。
この不規則な光の動きが、イタチにとっては「何か危険なもの」に見えるみたい。
具体的な方法はこんな感じです。
- 透明なペットボトルを用意する(1.5リットルから2リットルサイズがおすすめ)
- 水を8分目くらいまで入れる
- イタチが出没する場所の近くに設置する
- 複数のペットボトルを置くとさらに効果的
確かに、庭にペットボトルが並んでいるのは少し変かもしれません。
でも、イタチ対策と思えば、少しの我慢も必要ですよね。
工夫次第で、さりげなく配置することもできます。
この方法のポイントは、ペットボトルの向きを少しずつ変えること。
そうすることで、反射する光の角度が変わり、イタチを驚かせる効果が持続するんです。
まるで「キラッ!キラッ!」って光が動いているみたい。
注意点として、定期的に水を交換しましょう。
長い間放置すると、水が濁ったり藻が生えたりして効果が薄れちゃいます。
「えー、面倒くさい」って思うかもしれませんが、2週間に1回くらいの交換で十分です。
この裏技、実は一石二鳥なんです。
イタチを寄せ付けないだけでなく、夏場の猛暑対策にもなります。
水が蒸発するときの気化熱で、周囲の温度を少し下げてくれるんです。
「おっ、涼しくなった?」なんて感じるかも。
ペットボトルの水、意外な使い方でイタチ対策に大活躍。
身近なもので、効果的な対策ができるんです。
さあ、早速試してみましょう!
使用済み猫砂で「天敵の匂い」を演出!誘引率UP
意外かもしれませんが、使用済みの猫砂を罠の周囲に撒くと、イタチの誘引率がアップするんです。イタチにとって、猫は天敵。
その匂いを利用して、イタチを罠に誘い込む裏技なんです。
「え?使用済みの猫砂?」ってびっくりしますよね。
でも、これには理由があるんです。
イタチは警戒心が強い動物。
でも、天敵の匂いがすると、逆に興味を示すんです。
「ん?ここに敵がいるのかな?」って感じで近づいてくるわけです。
具体的な方法はこんな感じ。
- 使用済みの猫砂を少量用意する(新品じゃダメ!
) - 罠の周囲、30センチくらいの範囲に薄く撒く
- 風向きを考えて、イタチの通り道側に多めに撒く
- 2〜3日おきに新しいものと交換する
確かに少し匂いはします。
でも、イタチを捕まえるためなら、少しの我慢も必要です。
近所迷惑にならない程度に使いましょう。
この方法のポイントは、猫砂の量と鮮度なんです。
多すぎると逆効果。
イタチが警戒しすぎちゃうんです。
かといって、古すぎても匂いが弱くなっちゃう。
「ちょうどいい」加減が大切なんです。
面白いのは、この方法を使うと、イタチの行動パターンが変わることがあるんです。
普段より慎重に、でもちょっと興奮気味に動き回るんです。
「あれ?いつもと様子が違うぞ」なんて気づくかもしれません。
注意点として、猫を飼っている家の近くでは使わないようにしましょう。
猫が興奮しちゃうかもしれません。
「にゃんこごめんね」って感じです。
この裏技、ちょっと変わってるけど効果は抜群。
使用済み猫砂という意外なものが、イタチ捕獲の強い味方になるんです。
さあ、試してみましょう!
鏡の設置で「イタチの警戒心」を薄める驚きの効果
意外かもしれませんが、罠の周囲に鏡を設置すると、イタチの警戒心が薄れて捕獲されやすくなるんです。これ、本当に効果があるんですよ。
「え?鏡?」って思いますよね。
実は、イタチは自分の姿を鏡に映すと、仲間がいると勘違いしちゃうんです。
「あ、仲間がいる。安全だな」って感じで、警戒心が薄れるわけです。
この方法、具体的にはこんな感じで行います。
- 小さな鏡を用意する(手鏡サイズでOK)
- 罠の周囲、30センチから50センチくらいの位置に設置
- 鏡の角度を調整して、イタチの目線の高さに合わせる
- 複数の鏡を使うとさらに効果的
確かに、割れる可能性はあります。
だから、プラスチック製の鏡を使うのがおすすめ。
安全面でも安心です。
この方法のポイントは、鏡の向きと数なんです。
イタチがどの方向から来ても自分の姿が見えるように、少しずつ向きを変えて複数設置するのがコツ。
まるで「イタチ迷路」みたいですね。
面白いのは、イタチの行動が変わること。
鏡を見つけると、しばらくじっと見つめたり、不思議そうに首をかしげたりするんです。
「あれ?何だろう?」ってな感じで。
その隙に罠にかかっちゃうわけです。
注意点として、鏡の反射で周囲に迷惑をかけないよう気をつけましょう。
太陽光が強く反射して、ご近所さんの目に入ったりしたら大変です。
「まぶしっ!」なんてことにならないように。
この裏技、ちょっと不思議だけど効果はバツグン。
鏡という身近なものが、イタチ捕獲の強い味方になるんです。
イタチの習性を利用した、賢い捕獲方法。
ぜひ試してみてくださいね!